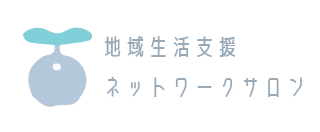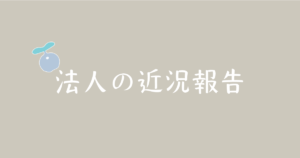新年度になりました
前回、新しい年になって、あいさつをしたと思っていたら、気づくと4月に突入して、新年度になっていました。
月1回は報告を書きたいといつも思っているのですが、日々の時間の流れにいつも飲み込まれています。
4月1日には昨年度高卒でぽれっこ倶楽部に新規採用になった若手職員から「今日で会社入ってちょうど1年」との嬉しそうな報告があり、お祝いの言葉の催促があったので、素直におめでとうと伝えました。
福祉の現場では人手不足が続き、なかなか若い人材が来なかったり、定着しなかったりすることが課題ですが、高卒で元気に楽しそうに働いている姿にとても励まされます。
さて、年度替わりの報告をいくつかしたいと思います。
ぽれっこ倶楽部の情報公開
昨年度の制度改正において新たに公開することになった「支援プログラム」をサイトに掲載しました。
また、「自己評価」についても令和6年度の分をぽれっこ倶楽部のページからダウンロードできるように公開しました。
全国的にも釧路の地域的にも年々、増えていく放課後等デイサービスですが、発達支援の質が問われています。ぽれっこ倶楽部もスペースを増やし、子どもたちにとってわかりやすいスペースやプログラムづくりに取り組んでいます。
ここでも何度か紹介しましたが、スタッフみんなでフローリングにしたり、先日はボールプールもつくりました。

ボールと一緒にビニールテープのポンポンが入っています。これはボールが足りなかったこともあるのですが、感覚遊びや刺激が必要な子どもたちのためにも混ぜたそうです。そして、このポンポンをグループホームで暮らす人たちが自由時間に作ってくれました。立派なおもちゃや道具を買ってきたり、プロに何かを作ってもらうこともできますが、プログラムが他の人たちの力の発揮の機会をつくりだしているところがネットワークサロンらしいと思います。
ぽれっと分場準備中
生活介護と就労継続支援A型の多機能事業所ぽれっとでは、事業所裏にある一軒家を全面改装して、分場を作っています。
ぽれっとの生活介護は重度の知的障がいや自閉スペクトラムの方たちと肢体不自由のある重症心身障がいの方たちが混ざって利用しています。2008年から3つの障がい(身体障害、知的障がい、精神障がい)が区別なく、サービスを利用できるようになりましたが、実際には法人や事業所によって専門分野のようなものがあったり、設備面の配慮も異なったりすることもあり、何となく利用者の障がい種別の傾向が分かれる方が多いように思います。
そんな中で、ぽれっと自閉スペクトラムの方たちと重症心身障がいの方たちがどちらも利用しているのです。様子を見ると、お互いの存在が刺激となったり、スタッフが幅広い介護や支援スキルを身に着けることができる効果もありますが、一方では難しい面もあります。
難しさの一つに利用者さんにとって「刺激」がどんな存在なのかという点があります。重心の方たちは強い刺激の方がいい、強くないと感じられないところがある一方、自閉スペクトラムの方たちはちょっとした刺激がものすごく不快のもとになったり、行動を誘引してしまうこともあります。
どちらも「刺激をコントロールすることが大切」という共通点があるのですが、その方向性がかなり異なるところがあります。
具体的には重心の方たちにはオーバーなリアクションで感情を前面に出しながら、顔を見て反応があるまで繰り返し声をかけた方がいいことが多かったりしますが、自閉スペクトラムの人にとっては絶対にやってはいけないような関わりになるだけではなく、自分への関わりではなくても、近くでそうした行為があるだけでも混乱のもとになってしまうこともあります。
そのような事情から、空間や刺激のコントロールという意味では今のぽれっとでは狭すぎたり、空間が少なかったりしていたという課題がありました。
その課題を解決するために裏の分場計画が進められています。
他にもA型の利用者さんの仕事の幅を広げることもできそうで、サービス内容の充実や改善そして、利用者さんたちの生活の質の向上とスタッフのスキルアップも図っていけたらと思います。6月ぐらいからスタートできそうなので、できたらまた写真付きで紹介したいと思います。
広域相談支援体制整備事業(釧路圏域)が続きます
昨年度からNPO法人縁とコンソーシアムを組んで実施している事業が今年度も引き続き、実施できることになりました。昨年度は、初めての年だったこともあり模索の1年でしたが、今年は2年目なので、昨年度の手ごたえをもとに、さらに充実させていく予定です。
特に、2月27、28日に実施した研修は、「意思決定支援」と「地域づくり」というテーマの重要性もありましたが、道東ブロック(十勝、根室、オホーツク)の同事業や振興局、帯広市などと連携や協働で実施したことに大きな意義を感じました。
今年度は研修事業を強化していく予定です。
新たに「こどもの居場所業づくり支援体制強化事業」に取り組みます
今年度の新たな取り組みとして、こども家庭庁からの補助事業「こども参画型オンライン居場所開発事業」を実施します。これは、これまで自殺対策の事業としてライフリンクと共同で開設し、細々と運営してきたサイト「生きづLABO」を発展させるものです。
生きづLABOは質問箱を中心として、ユーザーの声を拾ってきたのですが、最近、目立って若年(特に小中学生)の参加が多くなってきたことから、このニーズに何とか応えたいと思っていた時に、こども家庭庁から、令和7年度(令和6年度からの繰越分)こどもの居場所づくり支援体制の公募が出ているのを見つけて、関係機関とも調整のうえ、急いで応募をしたところ、採択を受けることができました。
応募の事業目的・内容には以下のように書きました。
サイト「生きづLABO」の成果を活用し、地域の居場所につながることが困難と考えられる孤立や排除状況にあるこどもたちがエンパワメントし、社会とつながることができる社会参加の機会を保障するため、こどもたちと共に居場所を創造、開発し、今後のオンラインによるこどもの居場所機能の役割や具体的なあり方について提案する
インターネットを活用して当事者の子どもたちの声や意見を取り入れ、リアルな人や場に子どもたちをつなげることができる(所属感を持てる)仕組みづくりを全国の仲間たちとも知恵を絞りながら進める予定です。
その他もろもろ…
それ以外にも、2~3月にかけて職員対象の虐待防止研修を何とか工夫しながら実施をしたり、広域相談支援体制整備事業でも触れた2月末の研修があったり、年度末にネットの居場所ポータルサイト死にトリのアプリ「とりぱーく」の内容が更新されたり、休眠預金のプロジェクトメンバーで「セクシュアルマイノリティと医療・福祉・教育を考える全国大会」に参加したりと、年度末にいろいろなことが集中し、駆け抜けた感があります。
次回は虐待防止研修について成果報告したいと思います。