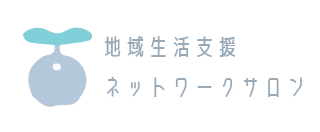ようやく秋になりました
釧路でも暑い夏が終わり、秋になったと思いきや冬の足音が聞こえてきそうです。
8月、9月、そして10月がものすごい勢いで駆け抜けています。
理由としては、8月30日と10月11日に外部講師を招いて、参加者を募って実施する連続講座を実施していたことと、いろいろな経過があり、一時保護委託で乳児を預かることになったのが重なった影響が大きいです。
子育ての大変さと分かち合いの大切さ
乳児の預かりは1か月とちょっと続き、私がメインで担当したことから、本当に久々に24時間3時間おきのミルクをはじめとして、赤ちゃんのケアを行うことの大変さを思い出していました。
やること自体にそれほど難しさや負担はないのですが、それがずっと続くこと、自分のペースではなく赤ちゃんのペースで一日を過ごすことで普段できることができなくなる(つまり自由がとても制限される)ことを感じ、改めて自由というものの存在や力を思い知りました。
赤ちゃんを育てながら、仕事もして、家事もしている世の中の人たち(いや、仕事や家事をしていなくても乳児の子育てだけでも十分です)に改めて心から敬意を抱きます。
本当に日々お疲れ様です。
同時に子育ては親という限られた人にお任せするのではなく、いろんな人たちで当たり前に分け合うことに重要性も感じました。
大変でしたが、関わった人たちで分かち合った経験は貴重だと感じましたし、赤ちゃん本人は覚えていないと思いますが、多くの人たちにとても可愛がられた感触はおそらく何かしら残っているのではないかと思います。
終わってみて、一時保護委託の仕組みの課題なども見えてきました。今後同様の状況で同じように受けられるかはちょっと悩ましいですが、そうした委託先が必要であることは実感しましたので、今後に向けて考えていきたいと思います。
連続講座の収穫
さて、もう一つのトピックである連続講座ですが、無事に8月30日の第1回目を終え、先日10月11日に第二回を終えることができました。
対外的なイベントはあまり得意ではなく、集客に苦戦しながらの実施でしたが、結果として主体的に参加してくれた人たちで比較的こじんまり(1回目は23名、2回目は34名)とじっくり話す機会を持ちながら実施できました。
1回目についてはプロジェクトのnoteで報告をしています。
【実施レポート】講座「恋愛/性愛の「当たり前」ってなんだろう?」(講師:As Loop 三宅大二郎さん)|くしろマイノリティ研究所
どちらも、少人数ではありましたが、遠方からはるばる来てくれた人もいて、嬉しい限りです。
また、講師で来てくれた三宅さんと髙木さんとはゆっくりと話す機会もあり、こうしたつながりがとても大切だと再認識したところです。
第2回の講師髙木さんには滞在中にいろいろなところを見てもらったり、滞在も休眠預金事業の新拠点で、当事者の集まりにも参加してもらい、釧路を「親戚の家のよう」と評されたため、体験記を書いてもらいましたので、紹介します。
髙木さんの釧路体験記
立命館大学衣笠総合研究機構・専門研究員の髙木です。この度は釧路市にお招きいただきありがとうございました。
始めはコミュニケーションについて考える市民講座の講師としてお声がけいただきました。NPO法人地域生活支援ネットワークサロン(以下、ネットワークサロン)さんが、ある人たちの生活を支えるために、実にたくさんの事業を通じて精力的にご活動されていることを知りました。そして、ご厚意で講座以外の日も釧路に滞在し、関連施設も見学させていただきました。
まずすばらしかったのは、施設にかかわるスタッフさんが、勉強熱心で、自分のこととして利用者さんを慮っていたのが印象的でした。関連施設で、スタッフさんと簡単な研修をしました。現在の学術的な発達障害の定義や、社会学の視点からコミュニケーションの問題をどのように考えられるか、神経多様性をどう考えるべきかについてなど、私自身の体験も踏まえてお伝えしました。
その後、日々の困りごとをお伺いする形で、スタッフさんと交流させていただきました。私も京都の支援施設に勤めて7年になりますが、私よりもずっと長い期間支援に携わっている大先輩が真摯に耳を傾けてくださり、内心恐縮していました。私の勤務先は私塾に近く、小規模で、個別の対応が中心ですが、ネットワークサロンさんは事業として多くのスタッフさんが多くの利用者さんを受け入れています。お互いの環境の違いを踏まえつつ、人を支えるという大きな目標に向けて、困っている人に今できることをすることと、長期的な視点から焦らずに関わり合う大切さについて、有意義な意見交換ができたと感じます。
滞在期間中、発達障害者と関わる方から、まだまだ未熟な私に「髙木さんにはどう見えますか?」とたくさんのご相談をいただきました。私のアドバイスがどこまで実際にお役に立つかは未知数ですが、支援者の方にも助けやケアが必要であり、「正解」かどうかはわからなくても、その試行錯誤に付き添い、不安な気持ちに耳を傾けられることは大切だということです。お話を伺っていると、支援をしている方の不安げな表情があるときぱっと明るくなるのです。本人への支援も大切ですが、支援者の支援の必要性についても、もっと取り組むべきだと感じました。
施設見学では、東京と並んで狭くて地価が高い京都から来たものですから、まず施設の物理的な広さとそれによって生じるゆとりに驚き、素直にうらやましい気持ちになりました。各施設が、それぞれの方の状態に合わせて使いやすいように設計され、清潔で、あたたかい空間に整えられていました。これだけ良い空間であれば利用者さんも過ごしやすいのではないでしょうか。たとえば、作業所での「トラブル」を度々小耳に挟みますが、その空間の許容量を超えた人数がいるだけで十分なストレスになりますので、実際のところ、物理的な不自由がそもそもの「原因」ではないかと思うときも多いです。北海道の雄大な土地に起因すると思われるパワーと豊かさを肌で感じつつ、京都をはじめ、他の土地で安心・安全な空間をどのように作っていくかについても考えさせられました。
講座では、主に自閉スペクトラム症(ASD)を題材に、個人の違いと、コミュニケーションそのものの「当たり前」という名の「思い込み」に気づく大切さについてお話させていただきました。当日はたくさんの方にご参加いただきました。発達障害当事者の方、支援者の方、恐らくご家族、赤ちゃんからお年寄りまでいろいろな人が一つの場所に集まってあるテーマについて考え、取り組み、意見を交わす機会が実現していることに、密かに感動していました。
特に、ワークの場面では、時間が足りなくなるほど参加者同士で会話が弾んでいるようでした。最近は、「心理的安全性」という考え方が注目されています。心理的安全性とは自分の気持ちや意見を安心して表現できる状態のことです。講座内ではお互いどれくらい違っているのか、どれくらいお互い勝手に期待してしまっているのか、どのようにすれ違ってがっかりするのかなど、コミュニケーションのむずかしさを扱いました。しかし、「むずかしさ」に気づきながら、それについて自由に話しているとき、私たちは間違いなくうまくやっていると思います。参加者のみなさんの会話が弾んだのは、まさに「むずかしさ」を起点にうまくつながりあっている証明に感じられ、大変嬉しかったです。
今回の滞在を通じて、たくさんの発達障害当事者の方と過ごし、親切にしていただきました。私自身も自閉症の診断を受けており、元気ですが、特性の影響も確実に受けています。たとえば、出発前日に台風の影響で飛行機が飛ばないかもしれないという情報を受けたときには軽くパニックし、親に電話をかけました。
このように、それぞれ苦手なことやできないこと、心身の不調などもあることを当たり前として、ネットワークサロンさんではさまざまな状態の人がその場にいました。そして、似ているところもあれば全然違うところ、わからないところもたくさんありました。それを笑って話せるのです。滞在中はいたるところで自然に「対談」「対話」がもたれ、その度に私も新しい自分を発見しました。
私(あるいは「私たち」)は、昨今話題の「共生」とか「多様性」を、つい壮大な目標としてとらえがちです。しかし、それは毎日の生活で実践されるものであり、いろんな人がいる「場」で起こるものだと感じます。ネットワークサロンさんは、そのコミュニティを当たり前に実現するために並々ならぬ努力をされているようにお見受けしました。その様子を見て、京都に戻った後、では私として何をするのか、できるのかについて、考えて実践していかなくてはいけないと宿題をいただいたような気持ちです。
最後に、私の持論をお話すると「スパルタコーチだ」と笑われました。私の考えは一般的な「支援」の基調となっている「ケア」とは少し違っています。もちろん、誰にとってもケアは大切です。しかし、少し元気が出てきたら、その人のよいところを見つけ、可能性を伸ばしていくことも同じくらい重要だと考えています。発達障害は治りません。でも、人は成長し必ず変わります。成長は時に少しの我慢や負担を必要とし、一朝一夕に起こるものでもありません。その間を、苦しい本人に代わって、安全を守りながら、誰よりも本人の可能性を信じて伴走するというのが、「支援」の醍醐味ではないかと感じています。
本人も周りの人も焦り過ぎず、生活を基盤に、丁寧に関わり合うこととそれを可能にする場づくりの可能性や大切さを、今回の滞在で学ばせていただきました。引き続き、専門的に学んだ者としてご協力させていただきたいと思います。この度は貴重な機会をいただき、本当にありがとうございました。
ちなみにスパルタコーチと評したのは私ですが、同じ文化圏(ニューロ圏?)の疎通性と理解のある中で鍛えることと、今回の講座のテーマでもある「見えない当たり前」が違い、社会的優位性(つまり権力)の格差がある中で鍛えるのではまったく意味が異なると思っています。
前者は正当な学ぶ機会になりますが、後者はハラスメントや暴力になってしまいます。同じことをやっているようで、実は構造的に違うということを今回の休眠預金のプロジェクトでは扱っています。
最後の11月29日はトータルに「見えない当たり前」を可視化して、私たち一人ひとりのマイノリティ性やマジョリティ性に気づき、社会モデルで自分たちの生きている社会を見つめることの重要性を実感する機会を持つ予定です。
改めて、講師の三宅さん、髙木さん、ありがとうございました。