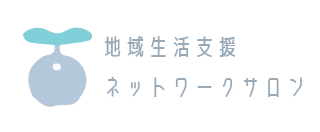釧路でも暑い夏
夏休みに入り、放課後等デイサービスや学習支援では夏休み企画で焼き肉をやっていました。しかし、よく考えてみると「夏に外で焼き肉」というのは北海道ならではの行事ですよね。
毎日猛暑のニュースを聞いて、北海道(もはや道東)以外に夏の焼き肉はそれは無理だろうと年々暑さが目立つようになっています。
これは今年だけのことではなく、今後も続いていくと思うと、暑さ対策もそうですが、そもそもの温暖化について本気で考えなくてはならない(今までも割と考えていた方ではあるのですが)と思っています。
法人全体で取り組むちょっとした脱プラもありそうなので、検討していきたいと思う暑い夏です。
市民として共に考える機会の重要性
さて、活動報告でもお知らせしていますが、8月30日に休眠預金のプロジェクトで講座を実施します。
共通するテーマとして「見えない当たり前を考える」で、今回は「恋愛と性愛の当たり前」について考えるものです。
「見えない当たり前」は休眠預金プロジェクトのメインテーマです。
詳しくは休眠預金事業の活動を発信しているnoteを見てください。
このプロジェクトではメンバーが活動の趣旨や方向性を深めるため2冊の本を読みました。
一冊はブラジルの教育学者であるパウロ・フレイレの「被抑圧者の教育学」で、もう一冊がアメリカの教育学者であるダイアン・J・グッドマンの「真のダイバーシティをめざして 特権に無自覚なマジョリティのための社会的公正教育」です。
今年に入ってから取り掛かり、先日ようやく2冊とも読み終えました。
読み終えて、考えて、話し合ったうえで、今回の講座が生み出されています。
これまでいろいろと研修をやってきましたが、コンセプトから課題意識まで事前にここまで考えたうえで企画をすることは初めてです。
しかも、今回は1回目で10月、11月には第2回、第3回とシリーズで実施します。
考えてみると、今回のテーマはネットワークサロンの設立趣旨やミッションが凝縮されているものなのかもしれないと思っています。
法人が設立されて25年が経ちました。
25年たっても、設立した当時と変わらない(さらに深刻になってるところも多々ある)社会の課題があり、それを他人事にしないで考え続けようとする姿勢があります。
その現場に若い世代の当事者性のある人たちがたくさんいることが私にとっては続ける動機になっています。
今年度にこども家庭庁からの補助事業をもらって取り組みを深めている生きづLABO でもサイトに来てくれる人たちに呼びかけて「研究員制度」を設立しようと公開の企画会議を行ったり試行錯誤をしています。
私たちの暮らす社会のこれからは一人ひとりの意識と行動にかかっている、今だからこそより市民活動のマインドが必要だと思っています。
公立大での新たな出会い
これら二つの事業の成果を携えて、6月には地元の釧路公立大にゲスト講義にも行ってきました。(先日の法人の活動報告で新人スタッフからのレポートでもこの講義をきっかけに働くことにつながった学生がいますが、その今年度版です)
休眠預金のコンセプト「見えない当たり前」を毎年テーマにしてきたのですが、上記の読み合わせ勉強会によって、見えない当たり前について普段考えていない人たちにどのようにわかりやすく伝えるのかというコツがつかめてきたので、これまでより手ごたえを感じました。
学生さんから毎回提出される「リアクションペーパー」にもその手ごたえが間違いでなかったことがわかりました。多くの学生さんたちが自分のことに引き付けて、テーマについて深く考える機会になったのが伝わってき、嬉しかったです。
何事も継続して実践することは大切だとも実感しています。
そして今年も当事者の学生さんがこの機会につながってくれました。講義後に大学の担当の先生に相談をしてくれたらしく、私たちの活動につながりました。
その学生さんが書いてくれたリアクションペーパーは今の社会を生き抜く若者の声が凝縮していると思ったので、本人の許可を得て紹介したいと思います。
「見えない当たり前=マジョリティの特権」について、NPO活動や実生活での体験を交えながらやさしく説明していただき、理解を深められたと感じます。大学入学後、差別・排除問題について少々触れる機会があり、今後も扱う可能性のあるテーマでしたので、文献の紹介も有難かったです。
私は、差別・排除というテーマには強めの関心と忌避感を持っています。それはおそらく、私自身がいくつか多数派から外れている属性を有しているためです。それでも最近は、特に大学入学後はこの分野についての興味関心が強まっていますが、まだ「知りたい・知るべきだがとても怖い・逃げたい」という思いがあります。
差別の原因を他者・社会に求めるより、全て自分のせいにする方が楽だからです。それは「自身でコントロール可能なものに責任を一元化すること」を意味しています。これによって世界の構造はごくシンプルになり、状況の認識や解析に使うエネルギーを節約できます。これほど楽なことはありません。私は今日をやりすごすのに精一杯で、声を上げる余力はありません。もはや抵抗する気も湧いてきません。だから結局、マジョリティ側前提の社会構造に甘んじ、不利益を受けているにもかかわらず自ら差別を助長しているわけであります。
当事者の活動を見ると辛くなるのは、「何故お前は何もしないのか」と責められているようだからです。
加えて、自身が現在の社会において不利な属性を持っていることを認めること自体も相当の苦痛を伴う行為です。自分の置かれている状況を認識し、受け入れることがなかなかできないでいます。いじめ、差別、排除に関する文献を読んでいると、不意に叫び出しそうになる(あるいは実際に叫ぶ)。自分が、生を受けた社会において、持って生まれた属性のために不幸になることが決定していただなんて、すんなり受容できません。それより、自分の意思の介在する行動の方に原因を求めた方がいくらかマシです。また、抵抗するかやりすごすか、どちらの赤字額が小さいだろうかと、ずっと勘定を試みている最中でもあります。
差別行為は誰にとっても不利益であり、特に行為者にとっては自縄自縛でしかありません。それは、将来その状態になる可能性を持つ自分への攻撃です。すでにある差別的な扱いに対して潜在的に恐怖を感じていることは、痛いほど理解できます。しかし、それでは悪循環が止まらない。差別撲滅は社会的リスクの排除です。マジョリティ側がそれに気づいて、能動的になることがどうしても必要です。
どうか自分自身の可能性を潰さないでやってほしい。あなたとあなたの大切な人たちが、この先どんな状態になっても穏やかに生きていけるように、と思うのに、あの人たちはこちらの話を聞きもしないし、こちらの存在すら認識していない。僕はずっとあなたたちの幸福を願っているし、あなたたちを理解しようとしていたのに。
現在の私は基本的に「疲れた、もう知らない!」という態度であり、未だ子供のように不貞腐れているので、もう一度起き上がるにはまだ少し時間がかかると思います。ですが、沈黙している必要がないことを目の前で示していただき、少しだけ元気になれました。貴重なお時間をありがとうございました。